もう今年も終わってしまいますね~。皆様どんなクリスマスを過ごされたでしょうか? 12月は原稿を書いたり雪の長野に出張に行ったりパーティに行ったり撮影スタジオの仕事や着付レッスンをしたり。あっという間に過ぎてしまったわにこです。大掃除?なにそれ食べられますか?
この1年、大好きな着物に関わる仕事がたくさんできたのでちょっと振り返ってみたいと思います。
1)このコラムの徒然をまとめた『
裏ワザ満載無理なく楽しむ オトナの着物生活』が発売になったほか、『
もめないための相続前対策 親が認知症になる前にやっておくと安心な手続き』(安田まゆみ共著)
『動画でわかる 誰でもカンタン楽ちん着付け』(髙橋和江著)の漫画やイラストを担当させてもらった!
2)SPILE ESSEN2024 ドイツでフォントかるたを袴姿で紹介した!
関連記事:
SPILE ESSEN2024 ドイツでフォントかるたを袴姿で紹介したよ!の巻
3)昭和な家スタジオ&きもの教室でたくさん着付けやレッスンができた!
10年前からカメラマンの渡部瑞穂ちゃんと一緒に運営している「
昭和な家スタジオ&きもの教室」では今年も素敵な撮影やレッスンをすることができました。
といっても、年初から3冊の書籍の漫画、イラスト、原稿執筆でぎゅうぎゅうになり、並行して定期で着方教室をしたり10月にはフォントかるたを売りにドイツまで行くというわにこ史上最も働いたイヤーとなっており、スタジオの仕事はぼちぼちという感じだったのですが、スタジオでやりたかったことが実現してきたな~という実感がありました。
それは「和装で家族写真」「和装で記念写真」を撮影してもらうということ。毎年秋以降は七五三と成人式の前撮りで忙しくなるのですが、主役だけでなくパパママにも着物を着て欲しい!という想いでプランにパパママ和装オプションをつけています。
スタジオをはじめたころは、お友達が記念撮影にきてくれるくらいだったのですが、ネットで探して七五三などの記念撮影にご利用くださるお客様が増えてきました。ホームページはわたしの手作りで、トップページにはわにこ作のポエムが書いてあるのですが、今年はじめて「感動しました」とのお言葉をいただき、すご~く嬉しかったです。
最初は七五三も成人式も、お母さんは着物を着てもお父さんはスーツというかんじでしたが、お父さんも羽織袴姿の写真をサイトやスタジオ前にもたくさん貼り出して「ぜひ全員で和装を!」とプッシュし続けた結果、この数年お父さんも当然のように和装をチョイスしてくださるようになりました。
いや~ほんと、胸アツです。だって数年前はどんなに「お父さんも着物どうですか?」と言っても固辞されまくっていたのに、このごろはお申し込み時から当然のようにお着物指定で、「5歳の時以来かも!」「はじめてかも!」とノリノリで着てくださいます。
そして、とっても似合うんですよね~!! パパも着物を着るのはうきうき楽しいことなんだ、って思ってもらえているようで私たちもとっても嬉しいです!
家族全員和装で撮影されるということは、私の着付人数も増えるということなんですが、準備と後片付けもなかなかのボリュームでこれは嬉しい悲鳴です。でも、撮影のときの皆さんの笑顔で全部吹っ飛びますね。
今年最後の撮影は、おばあさまの米寿のお祝いで息子さんご夫婦とお孫さんたちという総勢7名全員着物での家族撮影でした。お持ち込みの着物もあり、レンタルもありでしたが無事お支度もでき、とっても素敵な写真となりました。皆さん素敵でしたが、おばあさまの笑顔がそれはそれは素敵で、私もこんな米寿を迎えたいわ!と心の底から思いました。
あとは還暦振袖の撮影も楽しかったな~! 仲良しグループで来ていただくと盛り上がりが半端ありません。赤信号みんなで渡れば‥‥的な(いえいえそんなことはありません!)
来年も、たくさんの和装写真が撮れますように!
そして年末、もう一つ感動だったのが「年末のパーティに着物を着たいので」と11月の終わりにきてくださった30代の生徒さん。浴衣は着られるとのことだったので、自主練ができれば可能かな?とスタートすることに。
本番で着る訪問着と袋帯で練習を開始したのですが、補整から帯まで一通り説明したのち、着物よりまず最初に袋帯を結べるようにしてきてくださいと宿題を出した1回目。家で動画を見て毎日2回練習しました!と2回目には完璧に。2回目に丁寧に着物の着方をお伝えしてまたこれも復習しておでかけまでされたそうで、3回目にはもう30分で訪問着が着られるようになっていました。
そして、パーティに出席しましたと、素敵なお写真を送ってくださいました。子育てもお仕事もばりばりされているのに、すごい。すごすぎる。

いつも「着付は回数です」としつこく言っている私ですが、今回はそれに目標とやる気を付け加えたらすごい!(語彙)と目が覚めるような気持ちでした。
着物を着られるようになるにはどれくらいかかりますか?とはよく聞かれますが、「やる気次第」という回答もありだなと。あとは若いって素晴らしいな~としみじみしました。
着付もそれぞれ、自分ができるペースで取り組めばいい。順を追って覚えていく着付教室の他にも、自分の苦手なところだけ練習にきたり、これをするにはどうしたらいいの?なんてよろず相談にのれるスタジオでの着付け教室もやっていきたいな~と思っています。
時々私の本職ってなんだろうな?と思うことはありますが、やりたいことを精一杯やれることに感謝しつつ、来年はもう少し落ち着いて諸々丁寧に取り組みたいと宣言し(笑)今年のコラムを締めくくりたいと思います。
素敵な来年を思い浮かべつつ、よいお年をお迎えくださいませ。
 いつも「着付は回数です」としつこく言っている私ですが、今回はそれに目標とやる気を付け加えたらすごい!(語彙)と目が覚めるような気持ちでした。
着物を着られるようになるにはどれくらいかかりますか?とはよく聞かれますが、「やる気次第」という回答もありだなと。あとは若いって素晴らしいな~としみじみしました。
着付もそれぞれ、自分ができるペースで取り組めばいい。順を追って覚えていく着付教室の他にも、自分の苦手なところだけ練習にきたり、これをするにはどうしたらいいの?なんてよろず相談にのれるスタジオでの着付け教室もやっていきたいな~と思っています。
時々私の本職ってなんだろうな?と思うことはありますが、やりたいことを精一杯やれることに感謝しつつ、来年はもう少し落ち着いて諸々丁寧に取り組みたいと宣言し(笑)今年のコラムを締めくくりたいと思います。
素敵な来年を思い浮かべつつ、よいお年をお迎えくださいませ。
いつも「着付は回数です」としつこく言っている私ですが、今回はそれに目標とやる気を付け加えたらすごい!(語彙)と目が覚めるような気持ちでした。
着物を着られるようになるにはどれくらいかかりますか?とはよく聞かれますが、「やる気次第」という回答もありだなと。あとは若いって素晴らしいな~としみじみしました。
着付もそれぞれ、自分ができるペースで取り組めばいい。順を追って覚えていく着付教室の他にも、自分の苦手なところだけ練習にきたり、これをするにはどうしたらいいの?なんてよろず相談にのれるスタジオでの着付け教室もやっていきたいな~と思っています。
時々私の本職ってなんだろうな?と思うことはありますが、やりたいことを精一杯やれることに感謝しつつ、来年はもう少し落ち着いて諸々丁寧に取り組みたいと宣言し(笑)今年のコラムを締めくくりたいと思います。
素敵な来年を思い浮かべつつ、よいお年をお迎えくださいませ。
 いつも「着付は回数です」としつこく言っている私ですが、今回はそれに目標とやる気を付け加えたらすごい!(語彙)と目が覚めるような気持ちでした。
着物を着られるようになるにはどれくらいかかりますか?とはよく聞かれますが、「やる気次第」という回答もありだなと。あとは若いって素晴らしいな~としみじみしました。
着付もそれぞれ、自分ができるペースで取り組めばいい。順を追って覚えていく着付教室の他にも、自分の苦手なところだけ練習にきたり、これをするにはどうしたらいいの?なんてよろず相談にのれるスタジオでの着付け教室もやっていきたいな~と思っています。
時々私の本職ってなんだろうな?と思うことはありますが、やりたいことを精一杯やれることに感謝しつつ、来年はもう少し落ち着いて諸々丁寧に取り組みたいと宣言し(笑)今年のコラムを締めくくりたいと思います。
素敵な来年を思い浮かべつつ、よいお年をお迎えくださいませ。
いつも「着付は回数です」としつこく言っている私ですが、今回はそれに目標とやる気を付け加えたらすごい!(語彙)と目が覚めるような気持ちでした。
着物を着られるようになるにはどれくらいかかりますか?とはよく聞かれますが、「やる気次第」という回答もありだなと。あとは若いって素晴らしいな~としみじみしました。
着付もそれぞれ、自分ができるペースで取り組めばいい。順を追って覚えていく着付教室の他にも、自分の苦手なところだけ練習にきたり、これをするにはどうしたらいいの?なんてよろず相談にのれるスタジオでの着付け教室もやっていきたいな~と思っています。
時々私の本職ってなんだろうな?と思うことはありますが、やりたいことを精一杯やれることに感謝しつつ、来年はもう少し落ち着いて諸々丁寧に取り組みたいと宣言し(笑)今年のコラムを締めくくりたいと思います。
素敵な来年を思い浮かべつつ、よいお年をお迎えくださいませ。
 例えば振袖の帯締めの飾り結びも卒業式の袴のリボンも、左右どちらで結んでもいいのですが、私は左で結ぶようにしています。写真をとったとき目立つから! 基本は押さえた上で自分はこういう理由で左右選択している、と思うとなんかすっきりしますよね~。
着付けの最後にもう疲労困憊していてなんでもいいから結んどけ!みたいになりがちな帯締めですが、小さな面積でも体の中心で存在感があるものです。おしゃれの仕上げの要として楽しんでくださいね!
例えば振袖の帯締めの飾り結びも卒業式の袴のリボンも、左右どちらで結んでもいいのですが、私は左で結ぶようにしています。写真をとったとき目立つから! 基本は押さえた上で自分はこういう理由で左右選択している、と思うとなんかすっきりしますよね~。
着付けの最後にもう疲労困憊していてなんでもいいから結んどけ!みたいになりがちな帯締めですが、小さな面積でも体の中心で存在感があるものです。おしゃれの仕上げの要として楽しんでくださいね!
 羽織紐を結んだ時も同じです。羽織紐の場合は完全に
ぺったり平らにすると房の方向が定まって、全体が綺麗な形になります。
結び目を潰すか潰さないかで、仕上がりがかわります。六角形の結び目が綺麗にできていると、満足度大!です。
丸組や冠組の場合は不要ですが、平組の結び目を綺麗にしたいとき、最後に一手間かけてみてくださいね。
羽織紐を結んだ時も同じです。羽織紐の場合は完全に
ぺったり平らにすると房の方向が定まって、全体が綺麗な形になります。
結び目を潰すか潰さないかで、仕上がりがかわります。六角形の結び目が綺麗にできていると、満足度大!です。
丸組や冠組の場合は不要ですが、平組の結び目を綺麗にしたいとき、最後に一手間かけてみてくださいね。
 あと、着付けのときには汗もかきます。衿をあわせたら、てぬぐいをはさんで汗やファンデがつかないようにして帯を結ぶという方もいました。それもひとつですよね。また、紐や小物をしゃがまなくても手に取れるところに準備しておくのも大事です。
衿を合わせ終わったら、衿に指を通して少し肌と衿の間に隙間を作るのも衿汚れ防止には有効です。こちらもご参照ください。
関連記事:衿元を指1本浮かせるといいこと3つの巻
なるべく汚さないで、着物のお手入れも楽にしたいですよね。ちょっと動作を気をつけるだけでかなり防げる汚れですので、衿汚れに悩んでいる方がいらしたら参考にしてくださいね!
あと、着付けのときには汗もかきます。衿をあわせたら、てぬぐいをはさんで汗やファンデがつかないようにして帯を結ぶという方もいました。それもひとつですよね。また、紐や小物をしゃがまなくても手に取れるところに準備しておくのも大事です。
衿を合わせ終わったら、衿に指を通して少し肌と衿の間に隙間を作るのも衿汚れ防止には有効です。こちらもご参照ください。
関連記事:衿元を指1本浮かせるといいこと3つの巻
なるべく汚さないで、着物のお手入れも楽にしたいですよね。ちょっと動作を気をつけるだけでかなり防げる汚れですので、衿汚れに悩んでいる方がいらしたら参考にしてくださいね!

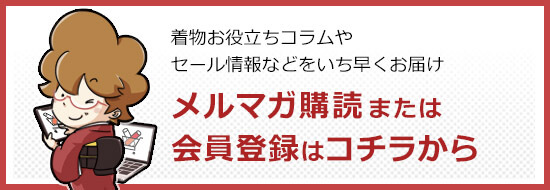

 Facebook
Facebook Instagram
Instagram Twitter
Twitter